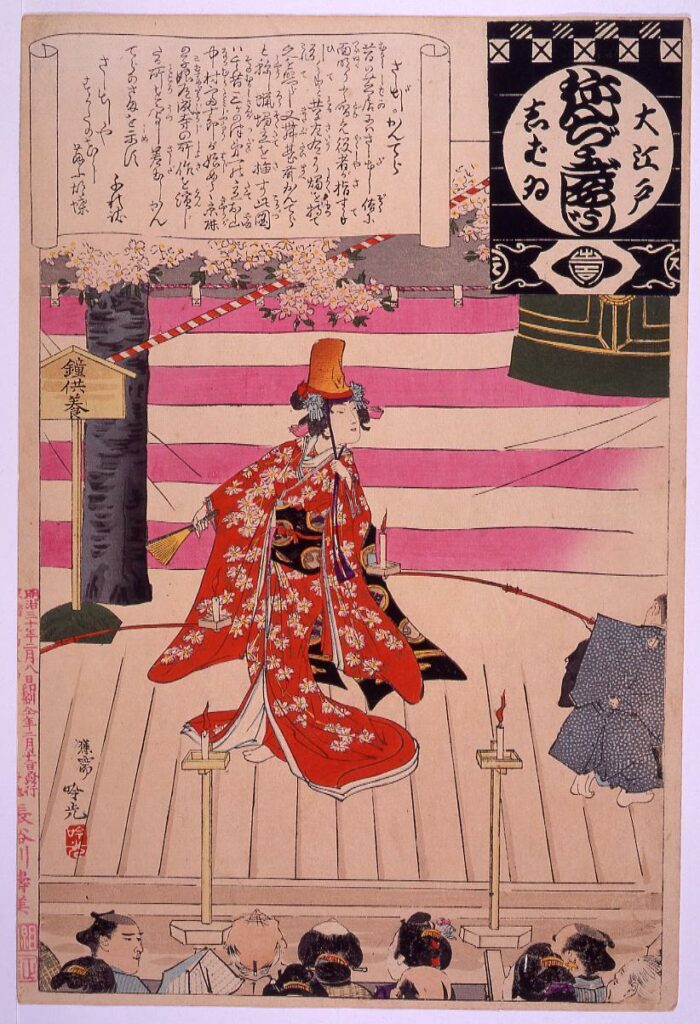
大江戸しばいねんぢうぎやうじ さし出しかんてら Annual Events of Theaters in Great Edo: Lit by Lanterns
鳥居清貞,安達吟光/画 Torii Kiyosada , Adachi Ginko
江戸歌舞伎の1年は、毎年11月から始まった。各劇場でこの年に出演する俳優を決め、その顔ぶれをお披露目する11月の顔見世は、最も重大な興行であった。芝居小屋には、座紋を描いた大提灯が「大入」の看板の両側につり下げられ、軒には小型の吊提灯が数百個も飾りたてられた。
ところが、意外にも舞台は暗かった。明治期になるまで、舞台照明は自然光が頼りだった。そもそも、芝居自体、朝から始まり、夕方に終わっていた。これは火事を防ぐためだったが、顔見世興行の際は夜明け前から始まるため、舞台照明は不可欠だった。こうした場合には、奉行所に使用許可願を申請すれば、灯火具の使用は可能だった。
芝居のなかで用いられる独特な灯火具がある。この錦絵で演者の左右から後見が差し出しているのが「さし出しかんてら」。二段になった長い柄の先に、ろうそくを立てる枡形の燭台がついたもので、大事な場面でさっと伸ばし、役者の顔だけを明るく照らし出す。今でいうスポットライトであった。四代目市川団蔵が、自分の顔をよく見せるために考案したとも伝えられる。現代の歌舞伎でも演出のひとつとして用いられている。
- 所蔵館
- 江戸東京博物館
- 資料名
- 大江戸しばいねんぢうぎやうじ さし出しかんてら
- 資料番号
- 91970058
- 種別
- 錦絵
- 作者(文書は差出人)
- 鳥居清貞,安達吟光/画
- 発行所(文書は宛先)
- 長谷川寿美/版
- 年代
- 明治後期 明治30年 1897 19世紀
- 員数
- 1枚
- 備考
- 91220155,91970048~91970073大江戸しばいねんぢうぎやうじ 全揃
- 江戸博デジタルアーカイブズ
- https://www.edohakuarchives.jp/detail-7843.html
江戸東京博物館のその他の収蔵品 (122294)

文化財調査写真 三輪大社
永江維章/編輯撮影
江戸東京博物館
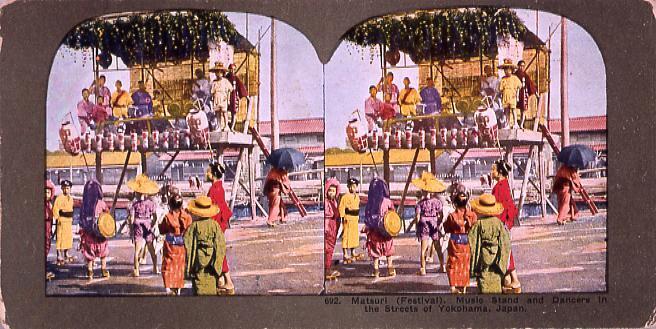
Matsuri(Festival).Music StandAnd Dancers in the Streets of Yokohama,Japan.692
江戸東京博物館
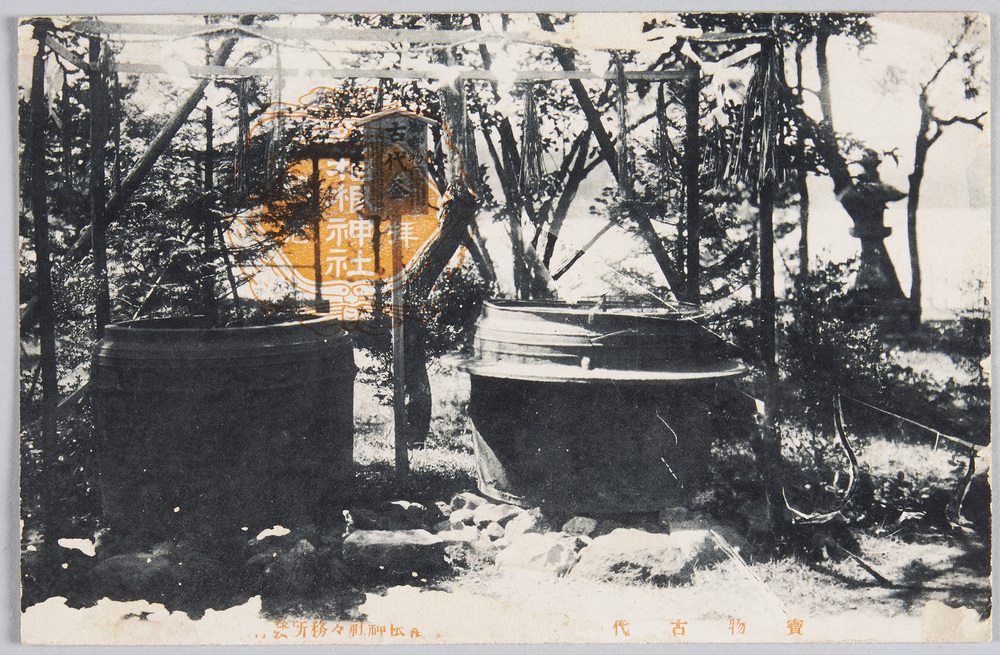
宝物古代釜
江戸東京博物館
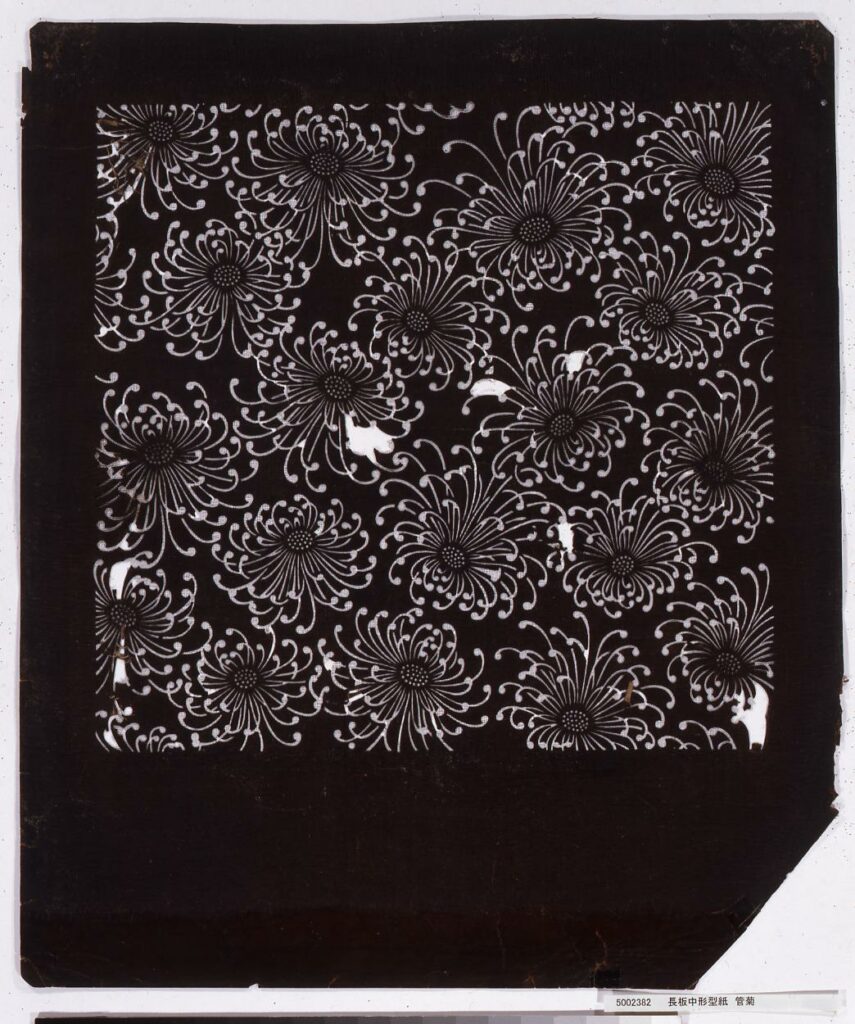
長板中形型紙 管菊
江戸東京博物館
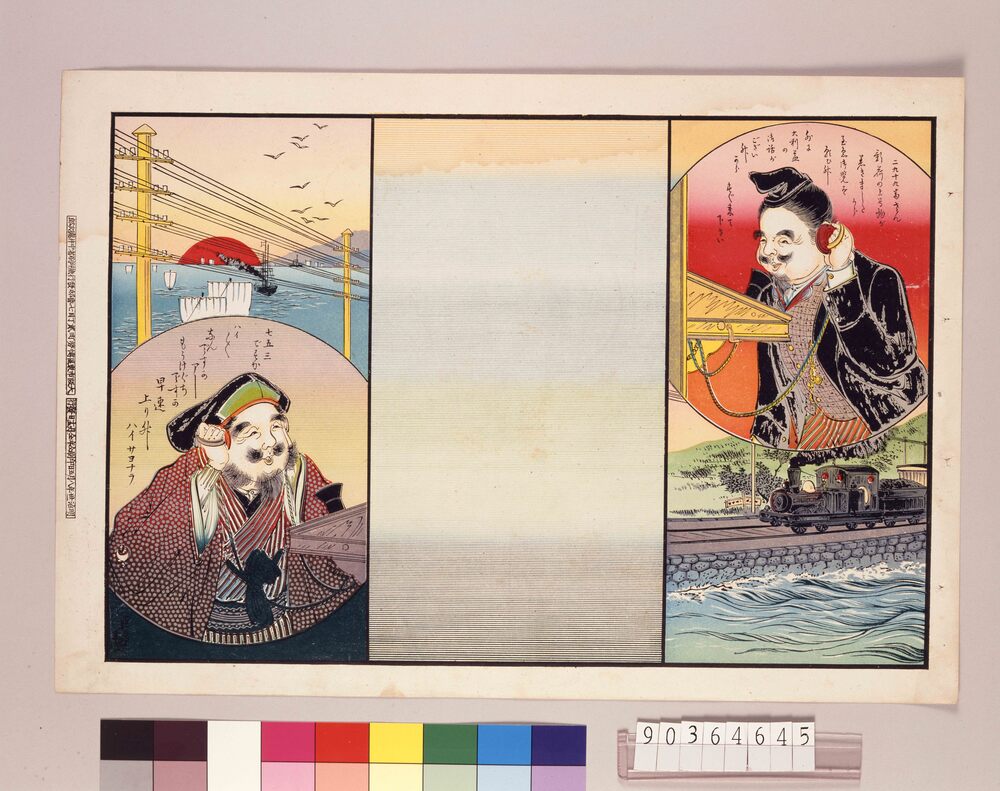
引札 ガワーベル戎大黒図
江戸東京博物館
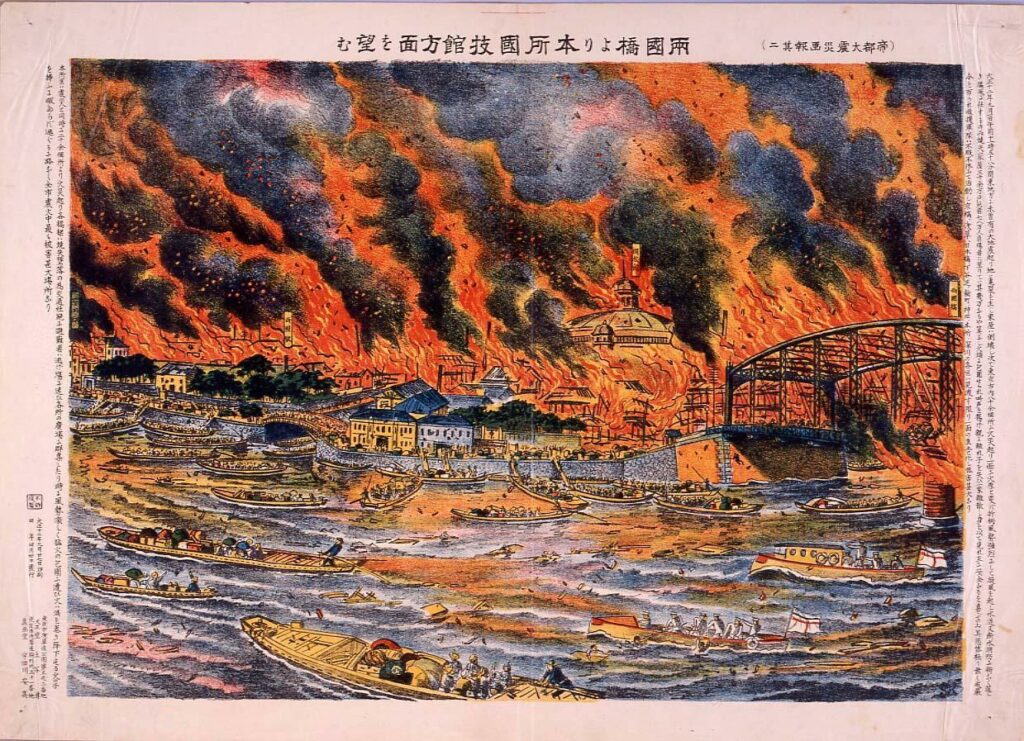
両国橋より本所国技館方面を望む
江戸東京博物館

セルロイド人形 踊り子風
江戸東京博物館
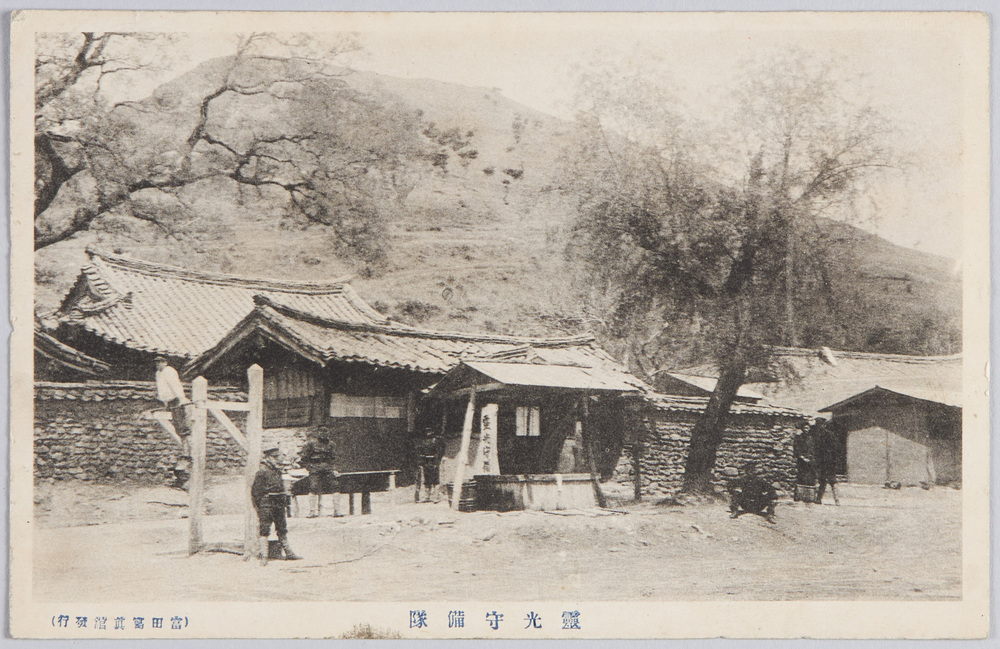
霊光守備隊
江戸東京博物館
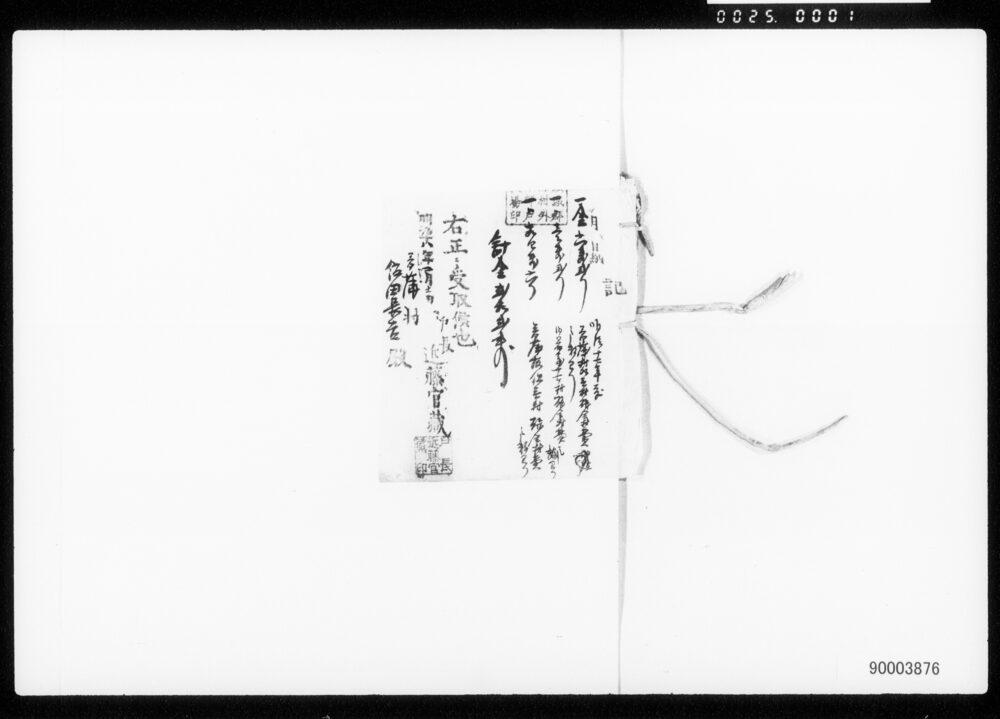
領収証一括
戸長近藤官蔵他/作成
江戸東京博物館

松方正義より永井久一郎(荷風の父)への書翰
松方正義/発信
江戸東京博物館
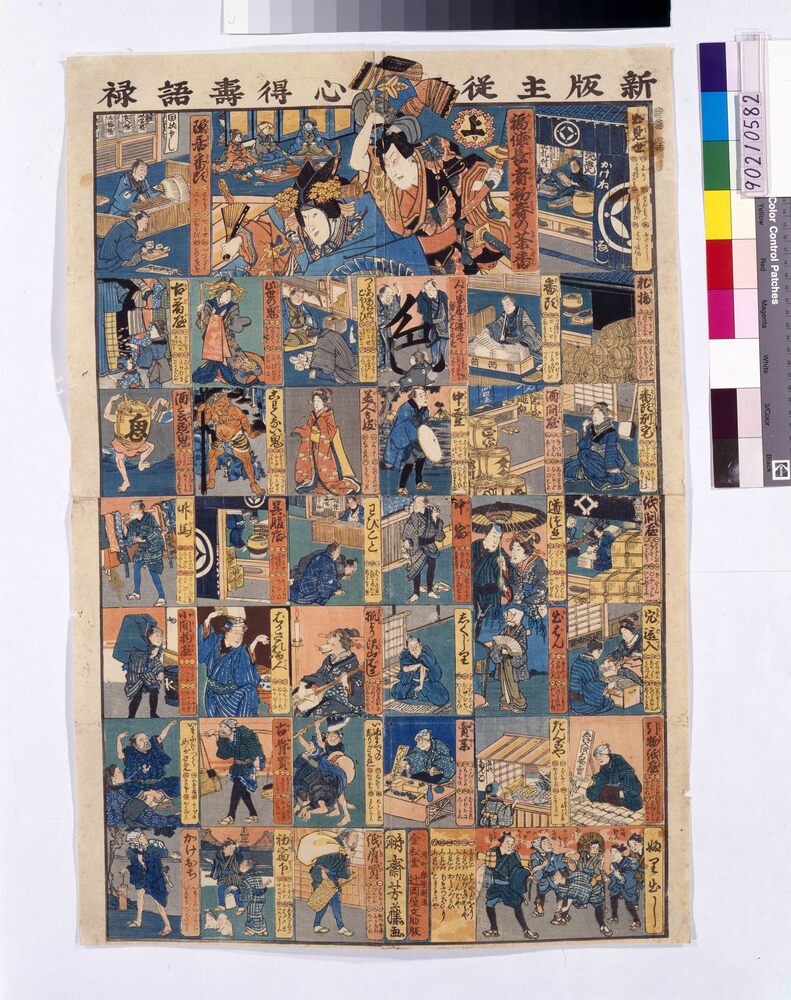
新版主従心得寿語録
歌川芳藤/画
江戸東京博物館

村は土から,みたから音頭
農山漁村文化協会/制定 古関祐而/曲 仁木他喜雄/編,農山漁村文化協会/制定 服部良一/曲・編
江戸東京博物館

末広五十三次 金谷
歌川広重(2代)/画
江戸東京博物館

216 だるまのやじろべえときだはち
清水崑
江戸東京博物館

ベルト
TANIWATARI/製
江戸東京博物館

市電乗換券 新宿-新車 間
江戸東京博物館

