
人力車は、和泉要助・鈴木徳次郎・高山幸助の3人が考案し、官許の上1870年(明治3)日本橋で開業したのが始まりという。江戸時代まで庶民の交通手段は徒歩か駕籠に限られていたので、人力車は文明開化を象徴する乗物となった。1896年(明治29)に全国の保有台数が21万台に達したが、この年をピークに人力車は衰退していく。鉄道馬車・自転車などライバルが出現したが、なかでも一番の打撃を与えたのは路面電車。線路が広がるにつれ人力車は減っていった。
- 所蔵館
- 江戸東京博物館
- 資料名
- 人力車
- 資料番号
- 90360001,90360022
- 大分類
- 生活民俗
- 小分類
- 交通商業
- 種別
- 交通運輸
- 年代
- 明治中期 明治25年 1892 19世紀
- 法量
- 183.0cm x 107.0cm x 198.0cm
- 資料群/コレクション名
- 赤木清士コレクション
- 備考
- 90360001 人力車:木製鉄輪・漆塗り・登録番号有り。 90360022 人力車 換え幌 仕様年代:明治30年代 変遷:大阪府八尾市東山本に住む貴族議員久保田家所有のもの。婚礼用具として伝来。
- 江戸博デジタルアーカイブズ
- https://www.edohakuarchives.jp/detail-57010.html
江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159767)
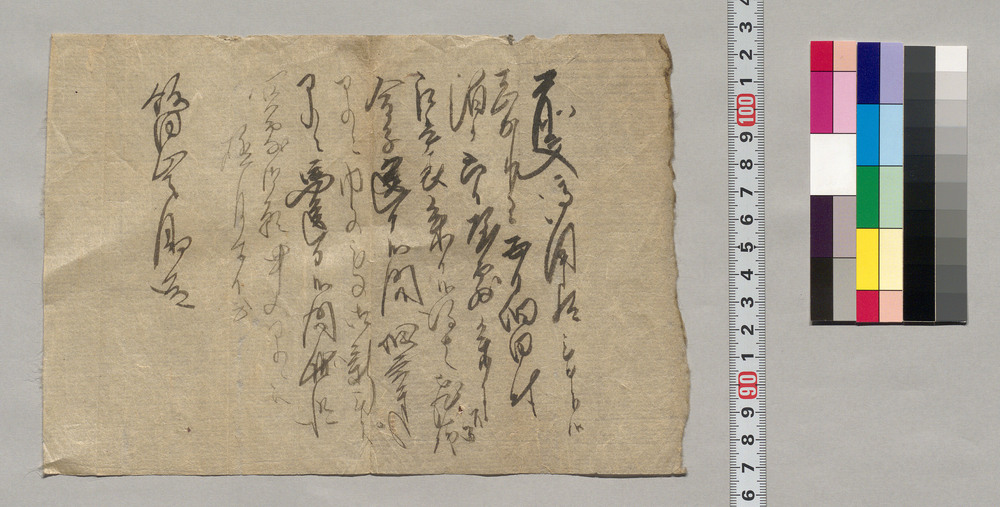
飯田山之助宛書簡(江戸表にて飛脚により金子送付の旨通知)
江戸東京博物館

分家契約証
(本家)渋谷亀蔵 (分家)村松久治郎
江戸東京博物館

横須賀鎮守府検閲済写真 本牧 三渓園
永江維章/撮影
江戸東京博物館

農村の子供たち 1
G・フェーレイス/撮影
江戸東京博物館
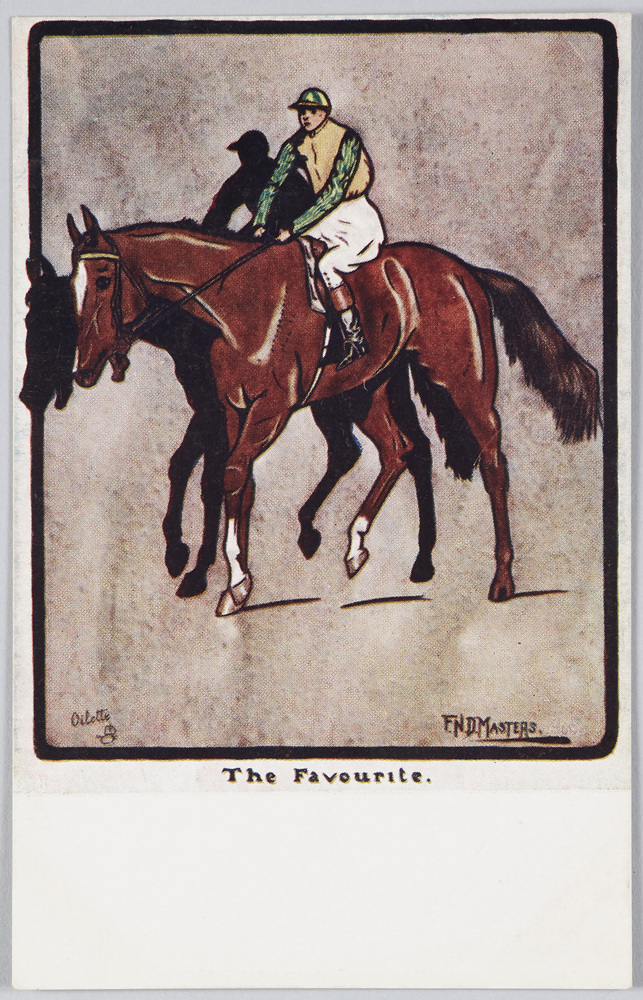
SPORT IMPRESSIONS
江戸東京博物館

東京劇場 昭和24年六月興行
松竹演劇部
江戸東京博物館

実地踏測番地入東京市街全図 附横浜市全図
日下伊兵衛/著
江戸東京博物館

膃肭臍丸
横山薬舗/製
江戸東京博物館
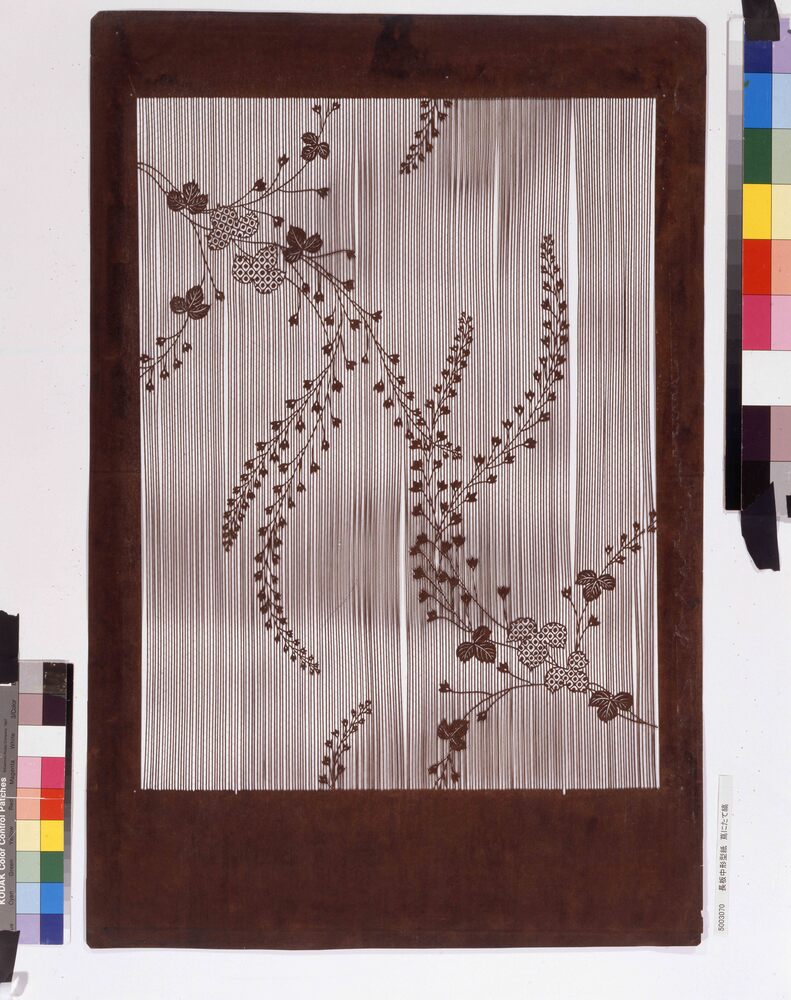
長板中形型紙 蔦にたて縞
江戸東京博物館

出納日記
高木はる
江戸東京博物館

昭和初期政治社会関係写真ニュース
江戸東京博物館

文化財調査写真 藤沢市郷土資料 飼養
永江維章/編輯撮影
江戸東京博物館
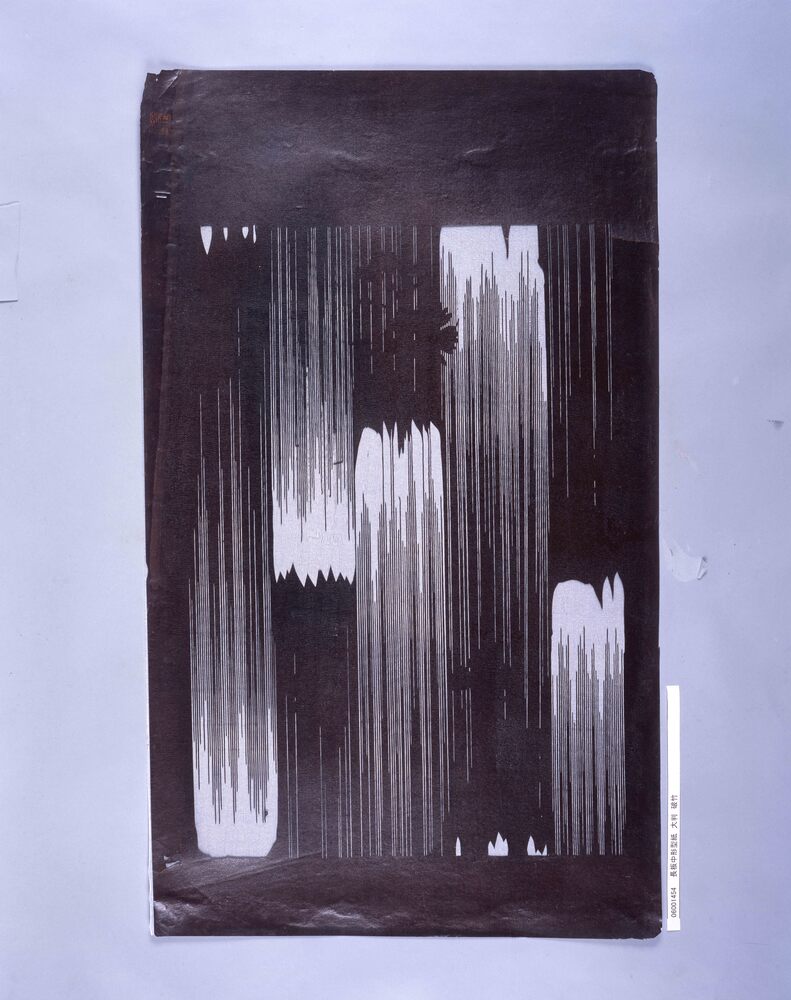
長板中形型紙 大判 破竹
江戸東京博物館

(65)フグとメザシの物語 さし絵
清水崑
江戸東京博物館
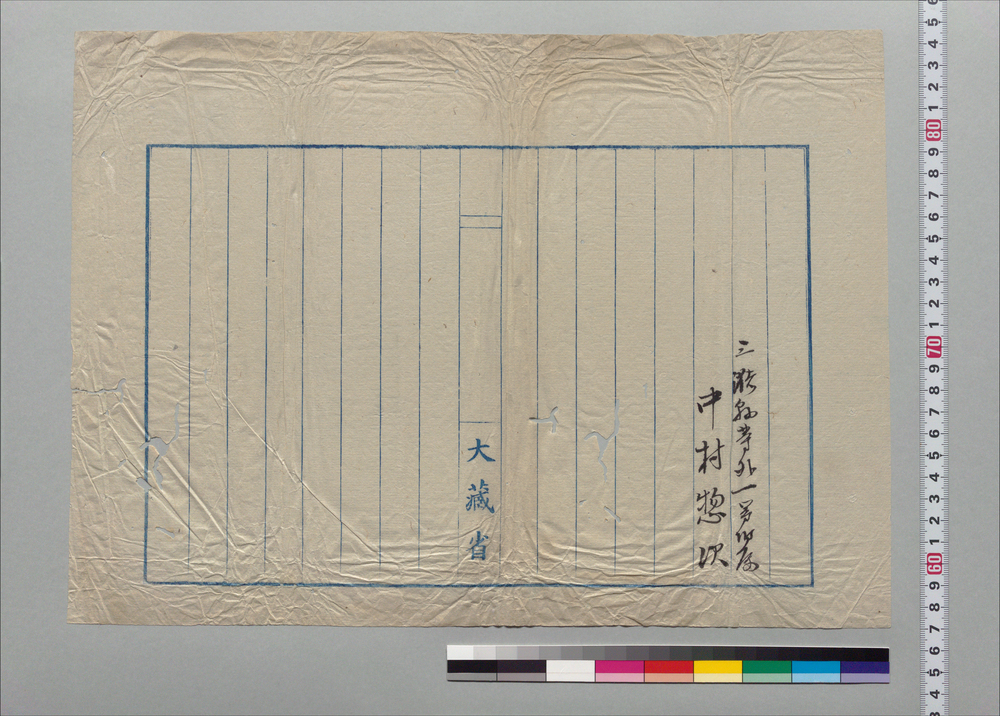
包紙(大蔵省罫紙反故)
江戸東京博物館

戦前風刺漫画 秋郊ナンセンス
細木原青起
江戸東京博物館

