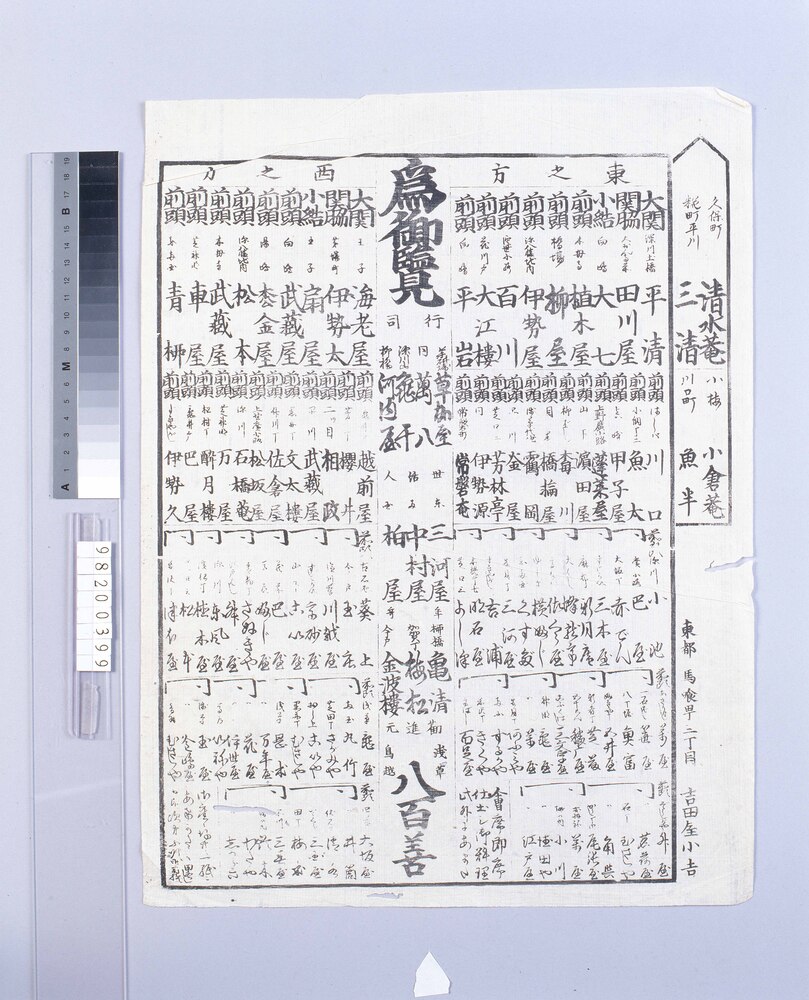
東西に分かれて上から順に大関、関脇……と格付けされた名前が記されているこの紙。相撲好きの方には馴染みのある番付と呼ばれる刷り物であるが、この番付、よく見ると順位付けされているのは「深川土橋 平清(ひらせい)」「浮世小路 百川(ももかわ)」と力士ではなく高級料理屋である。
江戸の町で高級料理屋の文化が花開いたのは文化・文政期(1804~1830)頃からだと考えられている。当時一流とされた店では、客はまず豪華な座敷に通されて、談笑しながら、しばしくつろぐ。そのうち風呂の用意が整ったと店の者から声がかかり、汗を流した後に料理を楽しんだ。
馴染みの客は大店の主人や文人たちが多く、料理屋は食事を楽しむ場だけではなく、文化的な社交場としての一面も持ち合わせるようになった。むろん贅沢なひとときには相応の値段がつき、百川では、一番下の位の膳で1人前約1000文したという。市中のそば屋の相場が1杯16文程度だったことを考えると、百川がいかに高額だったかがよくわかる。
中央の柱に行司や勧進元として連なる店名は、東西の順位付けには入らない、いわゆる別格とされていたものである。そこに配された八百善(やおぜん)は、文人たちとの交流を反映させて料理本を刊行するなど、江戸文化の発信の場でもあった。
- 所蔵館
- 江戸東京博物館
- 資料名
- 江戸割烹番付
- 資料番号
- 98200399
- 大分類
- 印刷物
- 小分類
- 刷物
- 種別
- 見立番付
- 発行所(文書は宛先)
- 吉田屋小吉
- 年代
- 江戸時代 19世紀
- 員数
- 1枚
- 法量
- 47.1cm x 35.3cm
- 江戸博デジタルアーカイブズ
- https://www.edohakuarchives.jp/detail-11922.html
江戸東京博物館のその他の収蔵品 (159764)
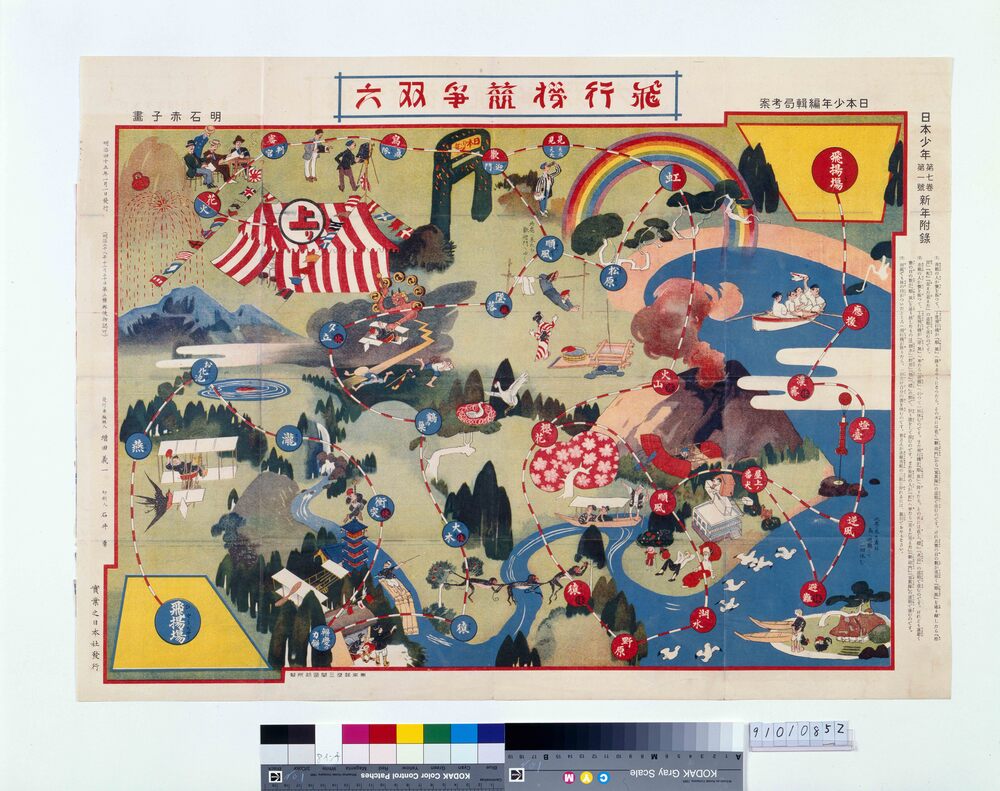
飛行機競争双六
日本少年編集局/考案 明石赤子/画
江戸東京博物館
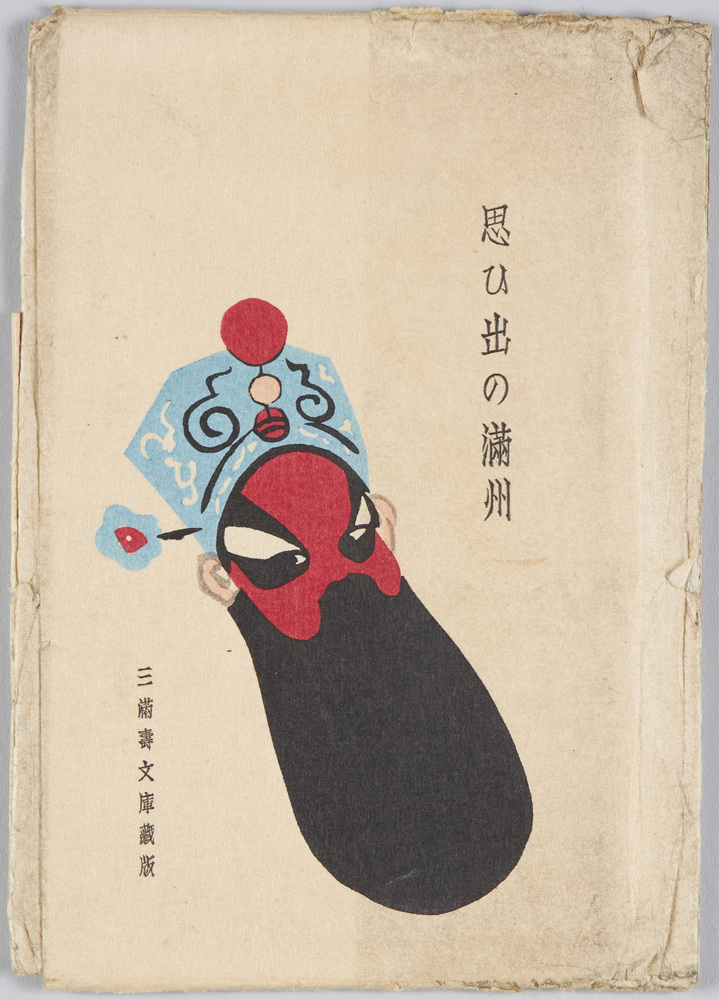
思ひ出の満州
江戸東京博物館
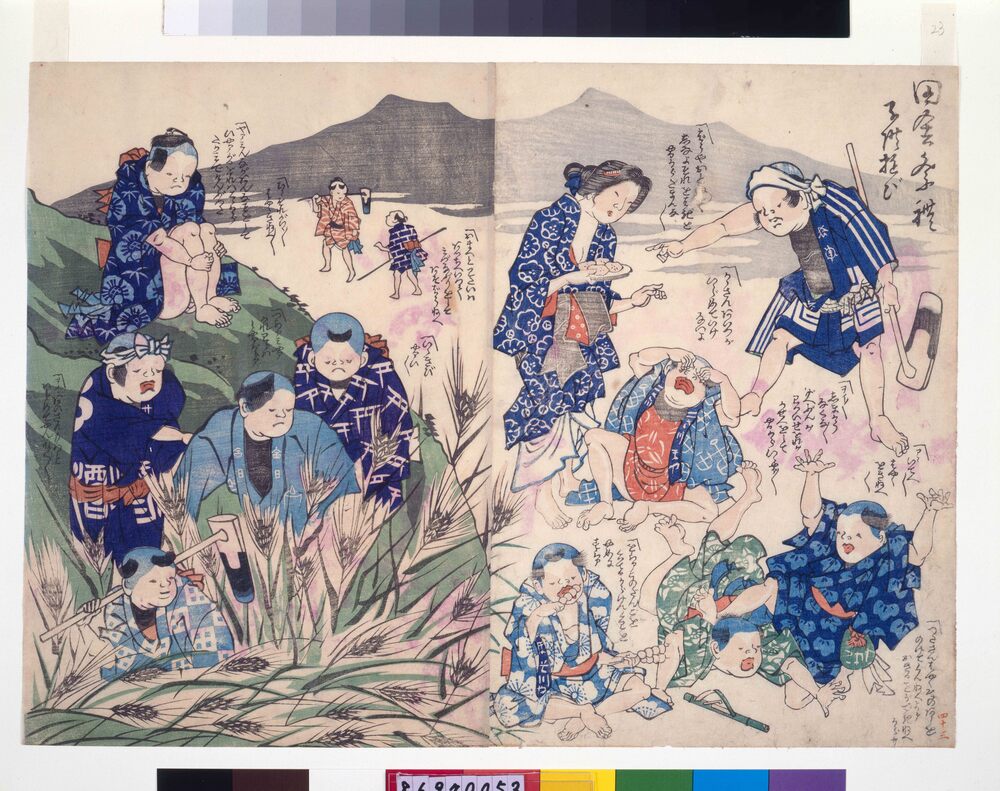
幕末頃子供遊絵 田舎祭礼子供遊び
江戸東京博物館

たばこ空箱(ピ-ス)
日本専売公社/製
江戸東京博物館

東京落語 かっぱの絵「1月」
清水崑
江戸東京博物館

三方
江戸東京博物館

野田町内自動車回数券
江戸東京博物館

印刷物 大阪乗合自動車株式会社株式申込証
江戸東京博物館

永井久一郎(永井荷風の父)像
Tamamura写真館/写
江戸東京博物館

角材(ダボ用)
江戸東京博物館
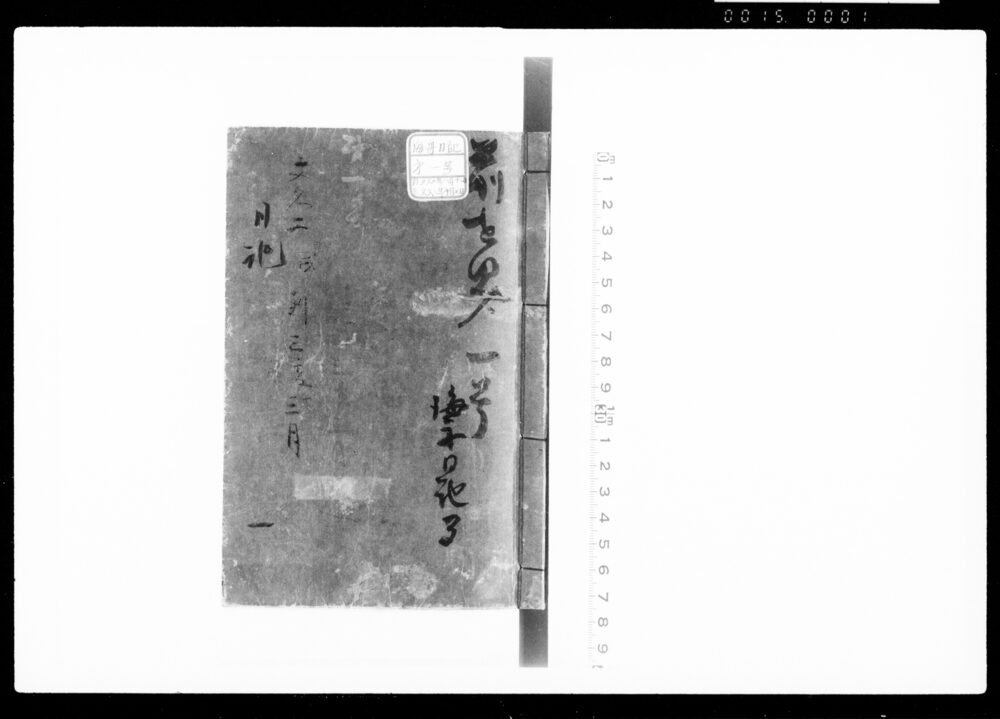
海舟日記
勝海舟/著
江戸東京博物館

グローブ ランプ部分
江戸東京博物館

土入れ 部分
江戸東京博物館

東京案内パンフレット 「颯爽とハイキング」
東京鉄道局
江戸東京博物館
![作品画像:[井上左太夫尋ねにつき砲術諸打方書付]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2025/07/686622-L.jpg)
[井上左太夫尋ねにつき砲術諸打方書付]
井上貫流/作成
江戸東京博物館

柳島橋 橋名板(竣工年月日)拓本
江戸東京博物館

